会社でパソコンを入れ替える前に考えるべき6つの判断軸 ― Windows10サポート終了に備える意思決定フロー
あなたの会社で使っているパソコンは、Windows10(ウィンドウズ・テン)ではありませんか?
画面の左下にある「スタート」ボタンを押し、歯車のマークから「設定」→「システム」→「バージョン情報」を開くと、「Windowsの仕様」という項目に「エディション」と「バージョン」が表示されます。そこに「Windows10」と書かれていれば、対象です。
このWindows10は2025年10月14日でサポートが終了しています。
サポートが終わるということは、新しいセキュリティ更新(ウイルス対策や不具合修正など)が配信されなくなるということです。
つまり、パソコン自体は動いていても、「安全に使えなくなる」リスクが出てきます。
そのため、会社としては「買い替える」「延ばして使う」「別の方法をとる」など、方向性を早めに決める必要があります。
この記事では、パソコンに詳しくない方でも理解できるように、会社でのパソコン導入をどう考えればいいかを、意思決定の流れ(フロー)に沿って整理します。
まず「目的」をはっきりさせる ― 買い替えなのか、延命なのか
パソコンの入れ替えを考えるとき、まず整理したいのが「なぜ今変えるのか?」という目的です。
実は、Windows10のサポート終了をきっかけに取れる選択肢は3つあります。
(1)買い替え:Windows11が使える新しいパソコンに入れ替える
買い替えがもっとも確実で、安心できる方法です。
最新の「Windows11」が動くパソコンは、セキュリティも強化されており、長く使う前提で考えるならこれが基本になります。
特に、事務・営業・経理など、個人情報や会社の内部情報などのデータを扱うパソコンは、このタイミングでの入れ替えが推奨されます。
(2)延命:今のパソコンをそのまま使い続ける
どうしても今すぐ買い替えが難しい場合は、一時的に使い続ける方法もあります。
このときのポイントになるのが「ESU(イー・エス・ユー)」という仕組みです。
ESUとは?
ESUとは「拡張セキュリティ更新プログラム(Extended Security Updates)」の略で、
有料でセキュリティ更新だけを延長して受け取る方法です。
要するに、「安全対策をあと数年だけ延ばす」ための仕組みです。
ただし、このESUは一時しのぎです。
- 使える期間が限られている(最長3年程度)
- 毎年料金がかかる(※条件を満たせば2026年10月13日まで無償で延長できます)
- 新しい機能や改善は含まれない
といった制限があるため、「今はまだ入れ替えられない」という会社が時間を稼ぐための方法と考えるのが現実的です。
(3)別のOS(オーエス)に切り替える
もうひとつの方法として、「ChromeOS(クロームオーエス)」「Linux(リナックス)」といった無料のOSに切り替える選択もあります。
ChromeOS/Linuxとは?
ChromeOSやLinuxは、Windowsの代わりに使える無料のパソコン用システムのことです。
※ChromeOSはインターネット接続が必須となります。
見た目や使い方は少し違いますが、インターネットやメール、文書作成など、基本的な操作は可能です。
たとえば、「会計ソフトはクラウド版を使っている」「印刷は少ない」「WordやExcelは閲覧中心」という場合は、無料のOSで十分使えることもあります。
ただし、Windows専用のソフト(例:弥生会計、販売管理ソフトなど)は動かない場合があるため、業務に合うかどうかを事前に確認する必要があります。
(4)まとめ ― “使い続ける期間”を基準に考える
選択肢を整理すると、次のようになります。
| 選択肢 | 向いているケース | 注意点 |
|---|---|---|
| 買い替え | 今後3年以上使う予定。長期的に安全に運用したい。 | 初期費用はかかるが、将来的に安定。 |
| 延命(ESU) | 1~2年だけ今の機器を使いたい。予算やシステムの都合がある。 | 基本有料。期間限定の対応。 |
| ChromeOS/Linuxに切り替え | ブラウザ業務中心。最低限の作業だけしたい。 | 一部のソフトが使えない。 |
買い替えずにそのまま使いたい → Windows11が動くかどうか
いま使っているパソコンを「買い替えずにそのまま使いたい」と思っても、
実際にWindows11が動くかどうかは、機種によって違います。
まずは「うちのパソコンは対応しているのか?」を確かめましょう。
Windows11を動かすためには、次の4つの条件を満たしている必要があります。
難しい言葉も出てきますが、ひとつずつ確認すれば大丈夫です。
(1)TPM(ティーピーエム)2.0に対応しているか
TPMとは、簡単に言うと「データを守るための鍵を保管する安全装置」です。
最近のパソコンには最初から入っていますが、古い機種では対応していないことがあります。
確認方法
- 画面左下の「スタート」ボタンを右クリック
- 表示されたメニューから「ファイル名を指定して実行」を選ぶ
- 名前の欄に tpm.msc と入力して「OK」をクリック
- 「TPMの製造元情報」という欄に「仕様バージョン: 2.0」と表示されていればOK
もし「TPMが見つかりません」などと表示された場合は、
設定で無効になっているか、古い機種で対応していない可能性があります。
(2)UEFI(ユーイーエフアイ)とセキュアブートが有効になっているか
これは、パソコンを起動するときに「不正なプログラムが動かないようにチェックする仕組み」です。
安全性を高めるために必要な設定ですが、古いパソコンでは無効になっている場合があります。
確認方法
- 画面左下の「スタート」ボタンを右クリック
- 表示されたメニューから「ファイル名を指定して実行」を選ぶ
- 名前の欄に msinfo32 と入力して「OK」をクリック
- 「BIOSモード」という欄に「UEFI」、「セキュアブートの状態」という欄に「有効」と表示されていればOK
設定を変える必要がある場合は、詳しい人やIT担当者に確認しましょう。
(3)メモリが4GB以上あるか
メモリは、作業中にデータを一時的に置く場所です。
数字が大きいほど、同時にたくさんのアプリを動かせます。
Windows11を快適に使うには、最低でも4GB以上(できれば8GB以上)が必要です。
確認方法
- 画面左下の「スタート」ボタンを右クリック
- 「システム」を選ぶ
- 画面中央上部に並んでいるボックスに「実装RAM」という表示があります
- 「4.00 GB」以上と書かれていれば条件クリア
もし4GB未満なら、Windows11には対応していません。
ただし、機種によってはメモリを増やせる場合もあります。
(4)CPU(シーピーユー)が新しい世代かどうか
CPUはパソコンの「頭脳」にあたる部分です。
古いCPUはWindows11に対応していません。
ざっくり言うと、2018年以降に発売されたパソコンならOKの可能性が高いです。
確認方法
- 「スタート」ボタンを右クリックして「システム」を開く
- 画面中央上部に並んでいるボックスに「プロセッサ」という表示があります
(例:Intel Core i5-1235U など) - Intelなら「第8世代(8000番台)」以降、AMDなら「Ryzen 2000番台」以降が対応目安です
例:
- Intel Core i5-8250U → OK(第8世代)
- Intel Core i5-6200U → NG(第6世代)
もし型番の数字が分かりにくい場合は、インターネットで「Windows11 CPU 対応リスト」と検索して確認できます。
(5)まとめ ― 4つすべてを満たしていればアップグレード可能
| 項目 | チェック内容 | 結果の見方 |
|---|---|---|
| TPM2.0 | 「tpm.msc」で確認 | バージョン2.0ならOK |
| セキュアブート | 「msinfo32」で確認 | 「有効」ならOK |
| メモリ | 「システム」から確認 | 4GB以上でOK(推奨8GB) |
| CPU | 「システム」から確認 | Intel第8世代/Ryzen2000番台以上 |
4つすべて満たしていれば、Windows11へのアップグレードが可能です。
どれか1つでも満たしていない場合は、買い替えや別の方法を検討する必要があります。
コラム:自動で調べる方法もある
Microsoftが公式で配布している「PC正常性チェックアプリ」を使えば、
これらの条件を一度に確認できます。
- 「Microsoft PC正常性チェック」と検索
- 公式サイトからアプリをダウンロード
- 「今すぐチェック」ボタンを押すと、結果が表示されます
この方法なら、細かい設定を開かなくても、
「Windows11に対応しているかどうか」がすぐにわかります。
会社の業態に合わせて、Windows 11 Pro か Home かを選ぶ
パソコンを購入するとき、「Windows 11 Pro と Home のどちらにしますか?」と聞かれることがあります。
見た目は同じWindowsですが、中身の機能には”会社向けか、家庭向けか”という違いがあります。
結論から言えば、
会社や事業で使うなら Windows 11 Pro を選ぶのが基本。
Home は個人利用向けに設計されており、セキュリティや管理の仕組みが制限されています。
(1)Home と Pro の基本的な違い
| 比較項目 | Windows 11 Home | Windows 11 Pro |
|---|---|---|
| 想定利用者 | 個人・家庭 | 会社・事業者 |
| セキュリティ機能 | 標準的な保護のみ | BitLocker(データ暗号化)・リモート制御など |
| 管理機能 | 個人設定が中心 | 会社全体の設定をまとめて管理可能 |
| 接続機能 | 家庭内ネットワーク | ドメイン参加・リモートデスクトップ対応 |
| 価格 | 少し安い | やや高い(2,3万円ほど) |
(2)会社で Pro を選ぶべき理由
① 情報を守る「BitLocker(ビットロッカー)」が使える
ノートパソコンの紛失・盗難時に、データを自動で暗号化して守る機能です。
Home には入っていませんが、Pro には標準搭載されています。
会社の顧客情報や経理データを扱う場合には必須です。
② 社内データの持ち出しを防ぐ「Windows Information Protection(ウィンドウズ・インフォメーション・プロテクション)(略して WIP)」が使える
Windows Information Protection(WIP)は、会社のデータと個人のデータを自動で区別し、社外への持ち出しや誤操作による漏えいを防ぐ機能です。
たとえば社員が自分のスマートフォンやUSBメモリにデータをコピーしたとき、
- 会社のデータは自動で保護(暗号化)され、
- 勝手に外へ持ち出したり、個人用アプリに貼り付けたりすることを防げます。
つまり、「うっかりミスで社外に情報を流出させてしまう」という人的ミスを防ぐための仕組みです。
USBや個人アプリへのコピーを制限し、情報を暗号化して保護します。
この機能が使えるのは Windows 11 Pro 以上 のみで、Home版では利用できません。
③ 会社全体で設定を統一できる
Pro では、ユーザーアカウントや更新設定をまとめて管理できます。
複数台のパソコンを同じルールで運用できるため、社員が多い会社や今後増やす予定がある会社に向いています。
(3)業態別のおすすめ判断基準
| 業種・業務内容 | おすすめエディション | 理由 |
|---|---|---|
| 不動産・建設・士業・製造業など | Pro | 顧客データの保護・社外接続・端末管理が必要 |
| 小売・飲食・受付端末など | Pro | レジ・POS連携やセキュリティ重視 |
| 個人事業主(1台のみ使用) | Pro(推奨) | 今後の拡張やリモート対応に備える |
| 家庭内での学習・趣味利用 | Home | 個人用途で十分、コストを抑えたい場合 |
(4)Pro を選ぶと将来の拡張にも強い
最初は1台でも、将来的に「スタッフを増やしたい」「ファイル共有をしたい」と考えている場合、
Pro を選んでおくと後からの設定変更や追加導入がスムーズです。
Home から Pro へ後で切り替えることもできますが、
その際は追加費用と再設定の手間がかかります。
(5)まとめ ― “業務で使う=Pro”が原則
| 判断の目安 | 選ぶべきバージョン |
|---|---|
| 仕事で顧客情報・会計データを扱う | Pro |
| 誤操作によるデータ漏えいを防ぐ | Pro |
| 社内で複数台を同じ設定で使う | Pro |
| 家族や個人の趣味・学習用 | Home |
パソコンを「会社の道具」として考えるなら、
Windows 11 Pro はセキュリティと管理の両面での安心保険です。
Home との価格差以上の価値があります。
「誰がどんな使い方をするか」を整理 ― スペック過不足を防ぐ
パソコンを選ぶときに、よく「スペック(性能)」という言葉を耳にします。
スペックとは、そのパソコンがどのくらいの力を持っているかを示す設計の内容のこと。
車でいえば「エンジンの排気量」「燃費」「荷物を積める量」などにあたります。
同じ会社でも、使う人の仕事内容によって求められる性能は違います。
営業担当が外に持ち出すノートパソコンと、デザイン担当が使う画像編集用パソコンでは、必要な力がまったく違うのです。
ここでは、パソコンの性能を見るときに知っておきたい基本用語をわかりやすく説明します。
(1)CPU(シーピーユー)=頭脳の速さ
CPUは、パソコンの「頭脳」にあたる部分で、
計算や判断など、すべての処理を行う中心的なパーツです。
- 例えるなら:「どれだけ頭の回転が速いか」という指標
- 表記例:Intel Core i3 / i5 / i7、AMD Ryzen 3 / 5 / 7 など
数字が大きいほど処理が速く、
たとえばメール・会計ソフト・ブラウザ作業が中心なら「Core i5」クラス、
画像編集や動画制作など重い作業をするなら「Core i7」クラスがおすすめです。
(2)メモリ=作業机の広さ
メモリは、パソコンが作業中に一時的に使う作業スペースです。
机が広ければ広いほど、同時に多くの資料を広げて仕事ができます。
- 例えるなら:机の大きさ
- 表記例:8GB、16GB、32GB
たとえば、
- 事務作業中心 → 16GBあれば快適
- デザインや動画編集 → 32GB以上あると安心
数字が大きいほど同時にたくさんのアプリを動かせます。
(3)ストレージ(SSD)=書類棚・引き出しの広さと速さ
ストレージは、データ(書類・写真・動画など)を保管する場所です。
ここが足りないと、すぐに容量不足になったり動作が遅くなったりします。
現在主流は「SSD(エス・エス・ディー)」というタイプで、
以前の「HDD(エイチ・ディー・ディー)」よりも静かで速いのが特徴です。
- 例えるなら:書類棚(収納)+引き出し(取り出しの速さ)
- 表記例:256GB、512GB、1TB
事務用なら512GB程度、
デザインや写真・動画を扱う場合は1TB以上をおすすめします。
(4)GPU(ジーピーユー)=画像や映像を描く力
GPUは、映像や画像をなめらかに表示するための装置です。
一般的な事務作業ではCPUに含まれているもので十分ですが、
チラシ作成や動画編集などを行う場合は、専用のGPU(グラフィックボード)があると動作がスムーズになります。
- 例えるなら:絵を描く専門のアシスタント
- 表記例:NVIDIA GeForce / RTX など
デザイン担当や建築図面、映像を扱う方に必要な項目です。
(5)ディスプレイ(画面サイズと解像度)=見やすさ
画面の大きさや鮮明さも、作業効率に大きく影響します。
数字が大きいほど表示領域が広く、細かい文字も見やすくなります。
- 表記例:14インチ、15.6インチ、27インチ/解像度 Full HD(フルHD)・2K・4K など
事務作業には15インチ程度が扱いやすく、
デスクワーク中心なら外部モニターをつなげて広い画面で使うのもおすすめです。
(6)OS(オーエス)=パソコンを動かす基本の仕組み
OSとは「Operating System(オペレーティング・システム)」の略で、
パソコン全体を動かすための土台となるソフトです。
Windows、Mac、Linuxなどがありますが、会社で業務ソフトを使う場合はWindowsが基本です。
また、会社で使うなら「Windows 11 Pro(プロ)」を選ぶのがおすすめです。
これはセキュリティ機能やリモート操作など、仕事に必要な仕組みが含まれています。
(7)Wi-FiとLAN=インターネットへのつながり方
Wi-Fiは無線、LANはケーブルを使った有線接続のことです。
最近のパソコンはどちらも使えますが、オフィスでの安定した通信を考えると、LANポート(ケーブル接続口)があると安心です。
(8)まとめ:使う人に合わせて「必要十分」に
| 使用者タイプ | 主な業務 | 性能の目安 |
|---|---|---|
| 事務・経理・総務 | 書類・メール・会計ソフト | CPU:Core i5 / メモリ:16GB / ストレージ:SSD512GB |
| 外回り営業・現場監督 | 写真・メール・資料共有 | CPU:Core i5 / メモリ:16GB / 軽量ノート |
| デザイン・制作 | 画像・動画・チラシ作成 | CPU:Core i7 / メモリ:32GB / GPU搭載 |
| 受付・POS端末 | 売上入力・顧客確認 | CPU:Core i3 / メモリ:16GBで十分 |
全員が高性能パソコンを使う必要はありません。
「使う人の業務にちょうどいい性能を選ぶ」ことが、無駄なコストを防ぐポイントです。
用途別に標準仕様を決めることが、コストを抑えるコツです。
「どこで使うか」を決める ― 据置か持ち運びか
ノート型・デスクトップ型の違いは、単なる好みではなく運用面の差です。
| 形状 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| ノートPC | 省スペース・持ち出し可能 | 落下・盗難リスク、拡張性が低い |
| デスクトップPC | 冷却・拡張性・価格が優れる | 設置場所が固定、停電時はリスク |
| 一体型 | 配線が少なくスッキリ | 故障時は全交換になる場合あり |
社内運用ならデスクトップ、出張や営業同行が多い職種ならノート型が現実的です。
設置場所の写真を撮ってから検討すると失敗が減ります。
「誰が管理するか」を決めてから買う ― 買って終わりではない
新しいパソコンを導入したあと、意外と大事なのが「管理体制」です。
どんなに性能の良いパソコンでも、使い方や設定の管理があいまいだとトラブルのもとになります。
- 社員が自分で設定を変えてしまい、共有フォルダにアクセスできなくなった
- パスワードがわからず、業務データを取り出せない
- 紛失・盗難時に情報漏えいの危険がある
こうした問題を防ぐには、
「誰が設定を行うのか」「どこにパスワードを保管するのか」を決めておくことが重要です。
管理を決める3つのポイント
- パスワード・BitLocker回復キーの保管場所
- アプリのインストール権限を誰が持つか
- 退職時・入社時のアカウント引き継ぎ方法
導入前にルールを作っておくと、後から混乱せずに済みます。
(1)BitLocker(ビットロッカー)とは?
BitLockerとは、パソコンの中に入っているデータを自動で暗号化(ロック)して守る機能です。
たとえば、ノートパソコンを外に持ち出したときに万が一なくしても、
この機能が有効になっていれば、他人が中のデータを見られないようにすることができます。
つまり、
- 鍵をかけた金庫のように、データを丸ごと守る仕組み
- Windowsの「Pro(プロ)」エディションに標準で入っている
- 一度設定しておけば、普段の操作は変わらない
という、とても便利なセキュリティ機能です。
(2)回復キー(かいふくキー)の保管が大切
BitLockerを有効にすると、設定時に「回復キー(かいふくキー)」という長い番号が発行されます。
これは、もしパソコンが壊れたり、Windowsを再インストールしたときに、
データを再び開くために必要な“スペアキー”のようなものです。
この回復キーをなくすと、中のデータを取り出すことができなくなります。
そのため、
- 紙に印刷して金庫や書庫で保管する
- OneDriveなどクラウド上に保存する(自動保存される場合もあり)
- 会社で管理する場合は、責任者を一人決める
といったルールを作ることが大切です。
(3)誰が設定・管理を行うかを決めておく
BitLockerのようなセキュリティ設定は、導入後に各自で行うとミスが起きやすくなります。
たとえば、複数の社員が同じパソコンを使う場合、
「誰が暗号化したのか」「回復キーがどこにあるのか」が分からなくなることもあります。
そのため、会社としては次のようにルールを決めておくと安心です。
| 管理項目 | 決めておく内容 | 備考 |
|---|---|---|
| セキュリティ設定 | 誰が初期設定を行うか | IT担当、またはスキルパスなど外部サポートでも可 |
| 回復キーの保管 | どこに、誰の名義で保管するか | 紙・USB・クラウドのいずれかで安全に保管 |
| アカウント管理 | 誰がパスワードや利用者変更を行うか | 入退社時の対応ルールを決めておく |
(4)まとめ ― 管理体制も“資産”の一部
パソコンは買って終わりではなく、
「安全に使い続けるための仕組み」まで整えてこそ、会社の資産になります。
特に、BitLockerを使ったセキュリティ対策と回復キーの管理は、
万が一の事故から会社を守る“保険”のようなものです。
導入前に「誰が・どのように管理するか」を明確にし、
必要であれば外部の専門家に設定を任せるのも有効です。
まとめ:買う前に「3つの質問」を
最後に、意思決定を整理する3つの質問で締めましょう。
- このパソコンはあと何年使う予定か?
- 使う人はどんな業務・環境で使うか?
- 買った後の管理とバックアップは誰が担うか?
この3点を決めてから購入に進むことで、
「とりあえず買ったけど使いにくい」「設定でつまずいた」といった
よくある失敗を防ぐことができます。
スキルパスでは
- 現在のPC資産の棚卸し
- 業務に合わせた最適スペックの選定
- 初期設定・データ移行・バックアップまで一括対応
を行っています。
久喜エリアの方、久喜市商工会会員の方を対象に、
・ご訪問での現地調査
・ご要望のヒアリング
・最適な導入計画
を無償にて行います。
→ [お問合せフォームはこちら]

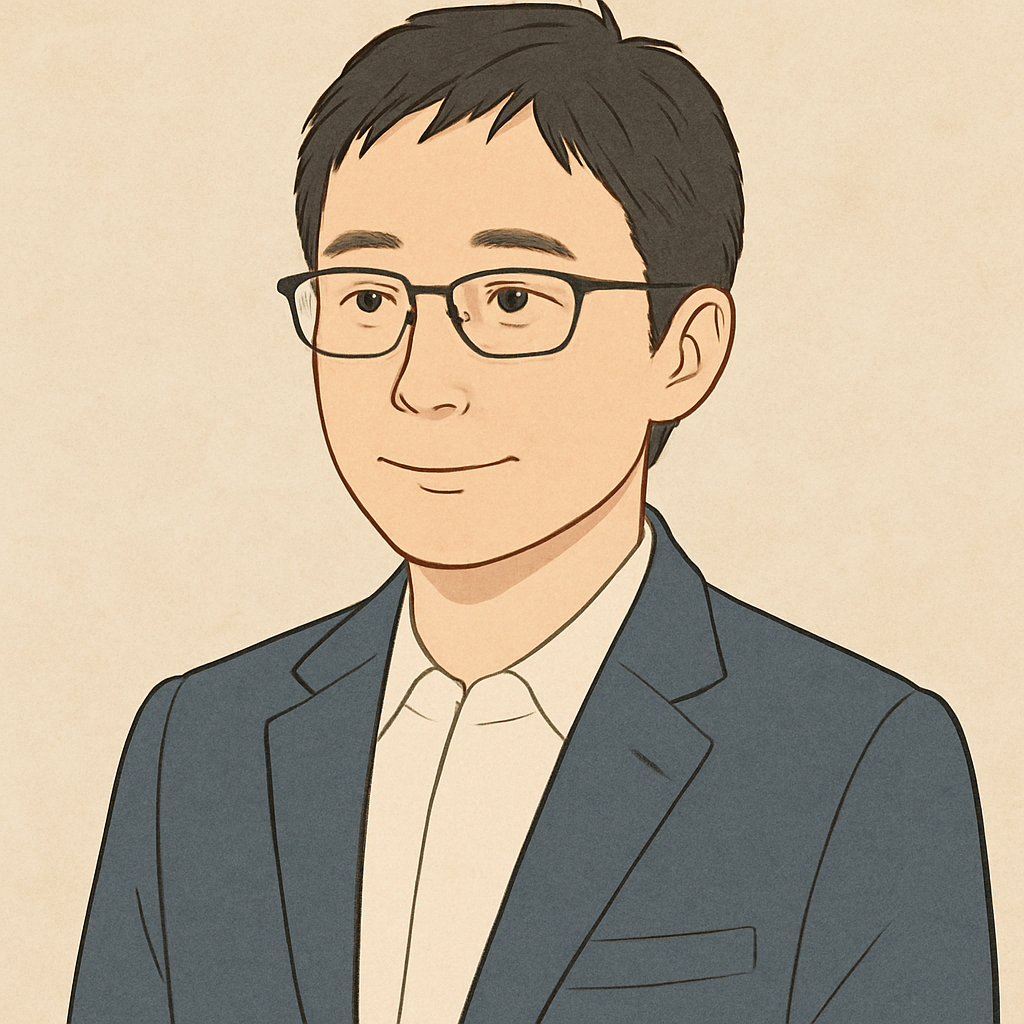


コメント